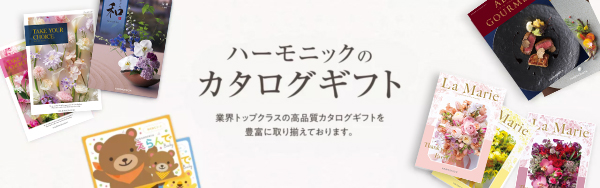出産祝いは、新たに家族が増えたことを祝うための大切な贈り物です。喜びを分かち合う機会であると同時に、思いやりを込めて対応することが大切です。細やかな配慮をすることで、相手に負担をかけず、真心のこもった気持ちがしっかり伝わるお祝いになります。この記事では、出産祝いにおける6つのマナー、おすすめのギフト、品物選びの注意点について解説します。

マナー①|出産祝いを贈る時期

贈るタイミング
出産祝いを贈る最適な期間は、赤ちゃんの「お七夜」(生後7日前後)から「お宮参り」(生後約1か月)までです。この時期は、出産後の回復が進み、退院して少し落ち着いていることが多いため、ギフトを受け取りやすい時期となります。
時期を逃した場合の対応
期間を過ぎてしまった場合でも、慌てず半年祝い(ハーフバースデー)や初節句、一歳の誕生日など、赤ちゃんの成長の節目に合わせて遅れたお祝いとして贈ると良いでしょう。その際には「遅ればせながら」と一言添えることで配慮が伝わります。
マナー②|出産祝いの贈り方

郵送が基本
退院直後は、母子ともに体力が少し戻りつつあるものの、外部との接触や対応がまだ負担になる時期です。宅配便で送ることで、訪問負担を軽減し、相手が都合の良いタイミングで受け取れるため好まれます。また、梱包をしっかりすることで衛生面も配慮できます。
直接渡す場合
相手から「直接お会いしてお祝いをいただきたい」と招かれた場合にのみ、手渡しが適しています。その際はマスクの着用、訪問時間の短縮、手指消毒など、感染や負担に配慮した準備が不可欠です。訪問前には一度連絡し、予定が変わった場合でもすぐに調整できるようにしましょう。
マナー③|訪問時の配慮

訪問前に確認する
日時が決まったら「授乳やお昼寝中ではないか」「リズムが安定しているか」「体調はどうか」といった点を確認します。赤ちゃんの生活リズムやお母さんの体調に合わせた日時設定が、思いやりある行動となります。
訪問時間と体調への配慮
赤ちゃんは授乳タイミングが短く、30分から1時間を超える訪問は相手に負担がかかることがあります。訪問は短時間に留め、手渡しだけして失礼するのが好ましいです。滞在が長くならないよう事前に伝えるとスムーズです。
感染対策と気遣い
マスク、手洗い、アルコール消毒を実施し、咳やくしゃみが出る場合は延期を考えましょう。また、訪問では「お母さんもゆっくりしてくださいね」「少し時間がずれてもかまいません」といった優しい声かけや気遣いの姿勢を示すことで、心地よい配慮が伝わります。
マナー④|のしや表書き

のし袋の種類と使い方
現金や商品券を包む際は、蝶結びの水引がついた祝儀袋(のし袋)を選びます。蝶結びは「何度あってもよいお祝い」にふさわしく、出産祝いに最適です。結びきりは繰り返すことを避けたいお祝い(結婚など)で使われます。
表書きと名前の書き方
「御出産御祝」を筆または筆ペンの黒で記し、その下にフルネームを記入します。連名の場合は、夫婦なら世帯主の姓と妻の名前を続け、友人間では五十音順、職場なら役職順で書くなど、正しい順序を守ることがマナーです。
中袋とお札の扱い方
中袋には金額と差出人の住所・名前を記し、新札を折り目なく入れます。肖像面を中袋の表側に向けて揃えることで、丁寧さが伝わります。折りしわがあると相手に手間をかけさせる可能性があるため注意が必要です。
マナー⑤|出産祝いメッセージ

心を込めたメッセージの伝え方
出産祝いに添える言葉は、相手への思いやりを込めた優しい表現を選びましょう。「すくすく元気に育ちますように」「無理せずお過ごしくださいね」など、気遣いが伝わるフレーズは受け取る側に安心感を与えます。また、「お会いできる日を楽しみにしています」といった未来への言葉を添えると、前向きな印象になります。
忌み言葉を避ける
「切れる」「失う」「消える」などの忌み言葉は避けましょう。これらは縁起が良くないとされる言葉であるため、慎重に言い回しを選びます。特に出産という新たな始まりを祝う場面では、前向きで温かい表現を心がけることが大切です。
マナー⑥|出産祝いの金額の目安

関係性別の一般的な相場
出産祝いの金額は、贈る相手との関係によって目安が異なります。たとえば家族、特に自分の子どもに贈る場合は3万円から10万円ほどが一般的です。兄弟姉妹であれば1万円から5万円、親戚には5,000円から3万円の範囲で贈られることが多いです。友人や職場の同僚には、3,000円から1万円程度が妥当とされ、上司や先輩など目上の方へは、5,000円から2万円程度が一般的な相場です。どの場合も、相手との関係性に見合った、無理のない金額を選ぶことが大切です。
縁起を意識した数字の選び方
金額を設定する際には、数字に対する縁起も考慮しましょう。たとえば「4万円」は「死」、「9万円」は「苦」を連想させるため、避けるのがマナーとされています。また、偶数は「割り切れる」ことから縁起が良くないと考える風習もあるため、どうしても偶数になる場合は「1万円と5,000円を2枚」など、工夫した金額の構成にするのが望ましいです。
負担をかけないための金額調整
相場から極端に外れた金額を贈ってしまうと、相手に気を遣わせたり、かえって負担を与えてしまうこともあります。高すぎる金額は恐縮させてしまうことがあり、逆に低すぎる金額は失礼に感じられる可能性もあるため注意が必要です。金額だけでなく、そこに込められた気持ちを大切にしましょう。
出産祝いにおすすめのギフト

タオルギフト
オーガニックコットン素材のバスタオルやフード付きタオルは、肌触りがやさしく、赤ちゃんの沐浴やお昼寝、おくるみとしても活躍します。吸水性が高く、洗濯にも強いため長く使える点も魅力です。シンプルなデザインからカラフルなものまで豊富に揃っており、出産祝いとして非常に贈りやすいです。
実用品セット
ハンドタオル、沐浴用品、ベビーケアグッズなど、実用的なアイテムを詰め合わせたギフトセットは、もらってすぐに使える点で好まれます。内容が具体的に想像しやすく、必要な場面で役立つものがそろっているため、贈る側としても安心感があります。
カタログギフト
何を贈れば良いか迷う場合は、カタログギフトを選ぶという方法もあります。受け取った相手が自分で必要なものを選べるため、相手にとっても使いやすく喜ばれやすい贈り物になります。育児用品、ママ用アイテム、ベビー服などが掲載されたカタログを選ぶと、出産直後から役立つものが揃っています。
出産祝い専用のカタログギフト「えらんで」

「えらんで」は、出産祝いにぴったりなカタログギフトで、赤ちゃん用アイテムはもちろん、ママのための癒しグッズや育児に役立つ日用品まで幅広く掲載されています。子供服や人気ベビーブランドのおもちゃ、ボディケア用品、マザーズバッグなど、実用性と品質を兼ね備えたアイテムが充実しています。さらに、赤ちゃんの月齢に応じたアイテムが分類されているため、成長段階に合わせた適切なプレゼントを選ぶことができます。

品物選びの注意点

誤解を招くおそれのある贈り物は避ける
ハンカチは「涙」や「手切れ」を連想させるため、出産祝いにはあまりふさわしくないと考えられています。また、実用性に乏しいものや、サイズが大きくて置き場所に困るインテリア雑貨なども、相手の生活スペースを圧迫するため控えた方が無難です。
サイズ選びとデザインの好みに注意する
スタイやベビー服などは、サイズやデザインの好みが分かれるため慎重に選ぶ必要があります。赤ちゃんの成長は早く、すぐにサイズアウトしてしまう可能性があるため、成長後も使えるようなゆとりあるサイズを選ぶか、消耗品のように「必ず使うもの」を選ぶのが安全です。色や柄もなるべくシンプルで上品なものを選ぶと、好みに左右されにくく安心です。
実用性と汎用性のある品を選ぶ
出産直後の育児で役立つもの、何枚あっても困らないタオル類、ベビーケア用品などは実用性が高く、贈り物として重宝されます。このように実用性が高く使い道が広い品物は、贈る側の気持ちが伝わりやすく、受け取る相手にも負担なく喜ばれやすい品になります。
まとめ

出産祝いは、新たな命の誕生を祝う気持ちを込めて贈る特別な贈り物です。贈る時期や方法、訪問時の配慮、のしや金額のマナーを押さえることで、相手に負担をかけず、気持ちがしっかり伝わるギフトになります。また、実用性の高いアイテムなど、受け取りやすいものを選ぶことも重要です。言葉や品物の意味にも気を配り心を込めて贈ることで、より喜ばれる出産祝いになるでしょう。
出産祝いならカタログギフトのハーモニックがおすすめ

出産祝いで当社人気No.1「えらんで」シリーズ